歌について考えてみる。自分用メモ(?)です☆◎歌全般に関して音とリズムが取れればそれでいいわけではなくて、自分は声を合わせるのが好きで得意なんだということに気づく。これは、合唱→アカペラの移行期に気づいたこと。あ、もちろん機会があれば、また合唱にも戻りたいです!◎アカペラに関して自分自身としては、合唱時代にアルトだったことも重なって、高音より低音の方がより好み。大まかにわけるとリード・コーラス・ベース・ボイパの中で、自分が活躍できる比率はこんな感じ。リード1点・コーラス7点・ベース2点・ボイパ0点経験地的には、リードがベースを上回ります。自分の声色が、目立つ声、というよりかは、声量が人よりそれなりにあり、且つ、溶けやすい声である、という点で点数をつけてみました。あ、ベースは、低い音を出せる&バンド全体を持ち上げているという役割上、至極好きなので、あとはリズム感さえつけられれば、という感じ。◎コーラスに関してコーラスでも1st〜4th、しかも、ガールズor混声によって役割が全然違って。例えば、リードだったら、曲の完成形をバンドメンバーの声でイメージして、コーラスに、こうして欲しいって要望をもっていきたい。んで、納得のいくリードが仕上がるまで原曲を聴いて、且つどこで遊べるか悩んでみる。このバンドでしかできない遊びをリードとしても、そしてコーラスとしても、またベースとしても取り入れることができる様に考える。1st,2ndだったらリードもしくは1stに声を合わせることに集中するし、混声バンドの中で一番低音(3rd,4th)だとしたら、男声&女声の区別がつかないように、バンド全体の和音をまとめる意識に集中する。4thだった場合、その役割に加えて、ベースとも声色をあわせることに集中する。ベースを担った場合はとくにそうだけど、リズムを走らないように心がける。コーラスだった場合は、リズムはベース&ボイパに徹底的に合わせる意識をする。どのパートを担う場合でも、意識があるのとないのとじゃ雲泥の差があって、意識することにより、前にはなかった習慣がつくようになったりする。例えば、リズム隊はこういうこと考えて打ってるんだな、だからもっと広がりをもって歌おうとか。他のメンバーの声を出すポジションはどこかなって探りを入れて、じゃあ、バンド全体の声をまとめるときには、自分はどのポジションでポジショニングをしてどんな風に歌えばいい、とか。◎編曲に関して自分は後天的理系だと思っているので(後天的理系っていうのは造語です)数を数えてキーボードを弾く。理論が頭に入ってないとなんにもならないので、理論本とキーボードを片手に、ひたすらPCとにらめっこ。このとき、歌ってもらう人がこだわるポイントがわかってれば、ある程度は譜面に書きおこしできるかな?とか。◎総括。編曲のときに学んだ理論は、歌うときにそれなりに役に立つし、歌っているときにどれだけバンドメンバーに意識を向けられるかによって、その後の自分の伸びしろが見えてきたり、編曲で使える知識を得たり、できる、と思う。あと、人の声にあわせることのできた時の快感。そのハーモニーをお客さんに伝えられることができたときの喜び。そういうのが大きくて、人とシンクロして(溶け合って)歌うのが好きです。だから、今のところコーラス大好き人間。ただし、低音もめっちゃ好きなので、できればベーシストとしても頑張りたい。新しい人と組むとき、そういう課題がそりゃあもう山積みになってみえるから、山を登るのが楽しい。人とシンクロしたときの喜びといったら!もう!だから、いろんな人と組んで、歌って、声を合わせていけたらいいなと思う。なんか色々書きましたが、要するに、歌ってすげぇや!ってことです。あー、ライブが待ち遠しいです。
歌について
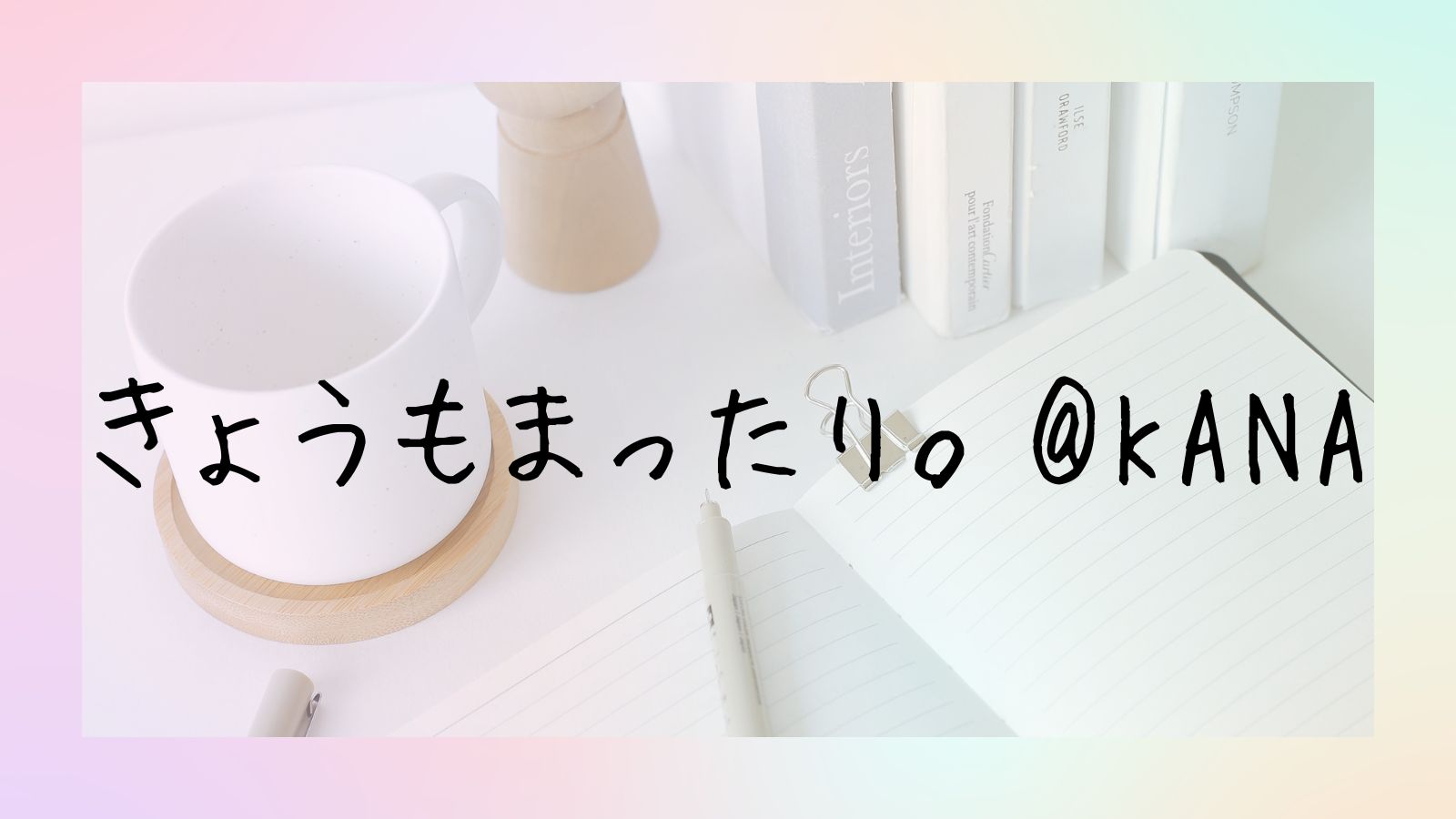 きょうもまったり。@KANA
きょうもまったり。@KANA
コメント