こんばんは!KANAです!
1月もあっという間に半分過ぎ去ろうとしていますね。
この冬はインフルエンザが大流行しているようですね。
かくいう我が夫も、
実は12月中旬あたりにインフルエンザに罹っておりました。
自分自身は、マスクをしながらとはいえ、
寝床は夫と同じ部屋だったにも関わらず、
全然まったく1mmも風邪をひく気配がなく、
すこぶる健康に過ごしました(笑)
皆さんも日々健康でありますように。。。!!!
そういえば、
新年に入ってしばらくしてから、
我が家でお餅をつきました。
「お餅をつきたいです!!」と会う人会う人皆に宣言しまくって、
自分自身への逃げ道を最初から塞いでの結果です(笑)
*お餅をつくのは力仕事だ!と理解していたので、
まずは気軽にもち米2合分から始めたのがちょうどいい感じになったのだと推測。
(レシピ通り3合から始めていたらついている段階でやめてたかも)
『そういえば幼少期は祖父母宅でお餅をつくのを手伝ったなぁ』
と、お風呂で思い出したのがキッカケ。
『昔の人が毎年お餅をついていたのだし自分でもできるに違いない!』
と根拠もなく早々にレシピを探すと、
検索結果の上のほうに、どこだかの百貨店の記事が出てきまして、
それが簡単そう&確実においしくなりそうという思い込みで、
このレシピで作ることに。
現代社会で餅つき機がなくても家庭で簡単につくれる方法は3つあるそうです。
1)電子レンジをつかう
2)炊飯器をつかう
3)蒸し器をつかう
私が参考にした記事では、1番はあまり推奨されていませんでした。
かといって、普段から料理に凝っているわけでもない我が家には蒸し器もない。
うむ、これはもう2番の炊飯器でいくしかあるめぇ。(唐突の江戸っ子)
というわけで、毎日お世話になっている炊飯器さんを頼りにすることにしました。
まず、米粒を水で洗います。洗って流れるお水が透明になるまでよく洗いますよ。
次に、お餅つきをする前日の23時にもち米2合ぶんを水に浸し始めます。
すると翌日の朝9時ころには米粒が水を吸ってやや大きめになったことを確認できました。
冬場のこの時期に暗くて寒いところ(←)に約10時間置きました。
そこで炊飯器さんの出番です。(我が家はZ〇JIRUSHIさんの小さな炊飯器)
お水の量は、色々調べてみた結果、『おこわ』の線の2合分でいいことが判明。
そのまま『白米』モード、つまり通常の炊き時間でスイッチオンです。
(いま話題の、アテにならないAIさんには、
水に浸したもち米の場合はおこわモードで炊いてください、とか、
他にも別の水分量で、とか、アレコレ言われましたが、全無視して通常モードで炊きました。
よいこはマネしちゃだめですよ☆
皆さんはそれぞれメーカーさんの説明書通りの水分量と炊飯モードで炊いてくださいね☆)
1時間後、ぴーぴー、と音が鳴りお米が炊き上がりました。
果たしていい感じになっているのでしょうか?
AIさんに言われたことをほとんど守らずに炊いたので、
実はだいぶ恐る恐る、、、炊飯器をあけます。
ぴかーーーー
おぉぉ、なんかもち米が、いい感じに光ってる!!!
うつくしい!!!
ここで用意したものは5つ!!
1)熱伝導率のいいボウル
2)ぬれた ふきん(餅つき中にボウルが動きにくくするため)
3)木でできためん棒(できれば水に浸けておく)
4)熱湯をいれておける鍋&熱湯1L
5)片栗粉(お餅を丸める作業をしている際に手にひっつくのを防ぐため)
さあ、いよいよ始めますよ、
念願の『餅つき』開始です!!
1のボウル下に、2の布巾を敷きます。
1のボウルにもち米を移動させます。熱々なので火傷にご注意を!
ボウルに入ったもち米を、3のめん棒でついていきます。
最初は餅をついている、というよりも、米を上から叩いているように感じるかも。
お餅はどんどん冷えて硬くなっていくので、
その都度4のお湯が入った鍋にボウルごと浸けたりして暖めてくださいね。
簡単に言うと お餅を湯煎にかける、みたいな? テンパリング?みたいな?
それと同時に3のめん棒にも、もちろんひっくり返すという作業をし始めた手にも、
お餅がべたべたとくっついてくるようになるので、
ちゃんとお水をつけつつ行ってください。
(私は寒がりなので後半は4のお湯にめん棒も手もいれながらやってました)
だんだんお餅がお餅らしく、もっちりとしてきます。
だんだんひっくり返すのも大変になってきます。
そういったときは、一人で無理せず人と交代でやったり、
力持ちのひとにつく方をお願いしてみたりしてくださいね。
ちなみに、我が家は途中から躊躇いなく夫を召喚しました(笑)
1人から2人へ。夫は男性なので私よりかは力持ちだし・・・。
一石二鳥でした。でへへ。(←)
30分もすれば、立派なお餅の出来上がりです。
最後に、5の片栗粉を手のひらにうすくのばします。
先ほども書いた通り、めん棒に水をつける理由&手に水をつける理由と同様、
お餅と手の融合を防ぐためです。
お餅は成型時に片栗粉がついているくらいがうまい具合に納まります。
あ、でもわざわざ片栗粉をお餅にはつけないでくださいね。
あくまでも成型をしやすくするためのコツなんです。
(因みにここで片栗粉ではなく小麦粉にすると
冷凍保存などをしていたお餅を食べる際に、お腹を壊します。
昔、祖母が言ってたんだから間違いないハズです)
人生初めてのお餅は2合から作ってみましたが、
最初は2合で本当にちょうど良かったです。
体力的にちょっと辛くなってきたな・・・、くらいで、
お餅が急にお餅らしくなってきますし、
そうすると俄然やる気になりますよね。
1回つくってしまえば、
3合だとどれくらい疲れるかな?とか、
自分や人とも体力を想像できますし、
次回作る時の目安にもできますしね。
それに我が家は夫と私しかいないので、量もちょうど良かったです。
と、いうわけで、
『普段料理なんかしないできないアラフォー女子が、
人生で初めてお餅をついてみた!!』
の回、これにて終了です!!
え、なに、写真が欲しいって?
気が向いたらきっとどこかでこっそりUPしますよ、たぶんね。
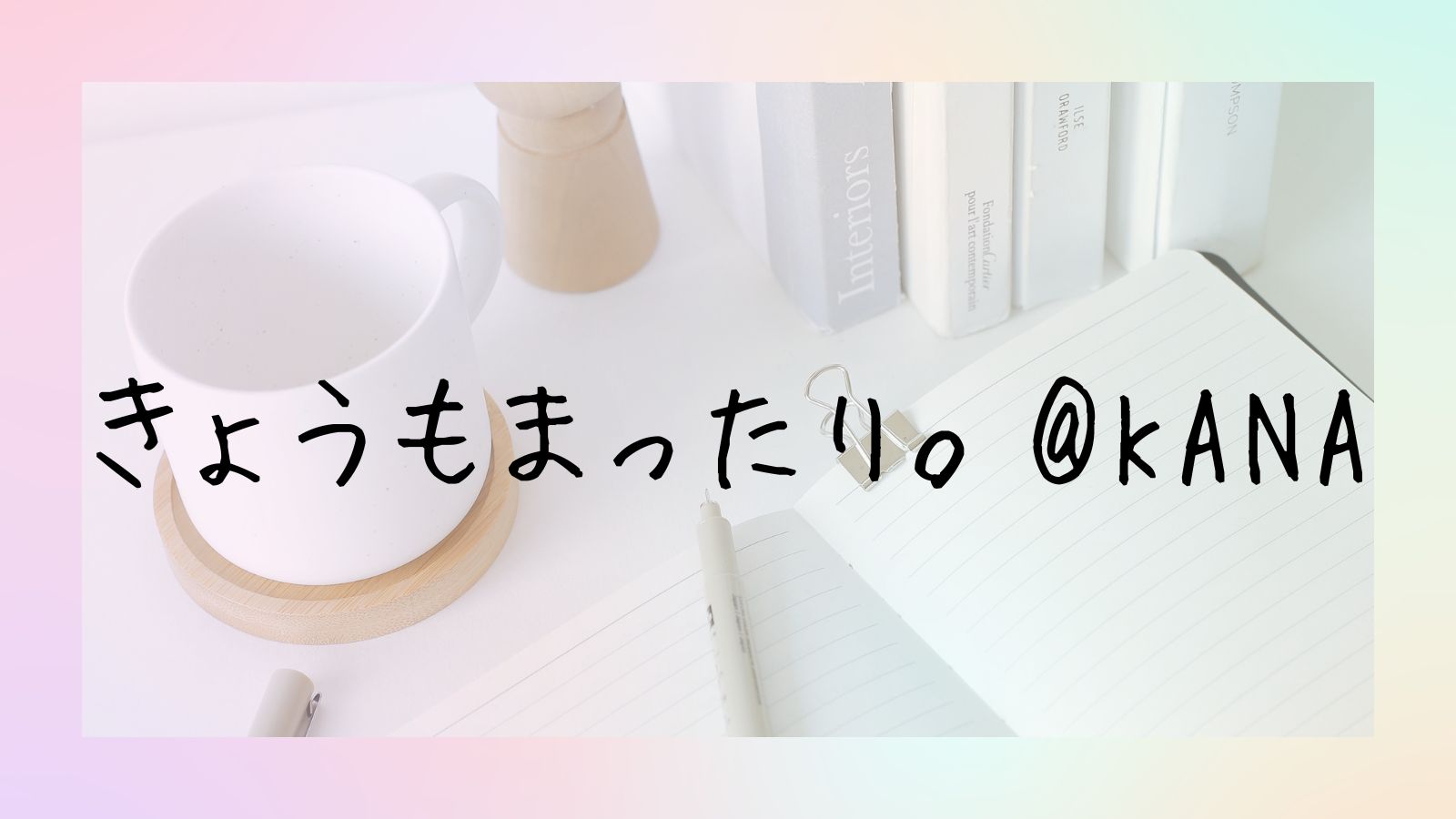


コメント