こんにちは、KANAです!
珍しくお昼に更新をしようかと、今日は早起きをしております。(←謎
この冬、機会がありまして、
年末から年明け1月にかけて、
たくさんの美術を堪能しています。
その中でも特に思いがけなかったのは、
なんと生の”浮世絵”!!
しかも出合った場所が美術館ではなく、
近所のエキナカの本屋さんの一角でした。
その日は、歯医者さんのために駅まで出た日でした。
歯医者さんの時間まで、まだ余裕があったため、
私はいつもの癖のように、本屋さんへ寄ろうと足を運びました。
本屋さんの出入り口に座っているおじさまとカラフルな色彩が目に入り、
「あれ?なんだろう?」
ふらふらとなんとなくそちらへ向かいました。
テーブルに広げてあるものは、
なんととっても素敵な浮世絵でした。
しかも教科書に載っているような退廃的なものではなく、
めちゃくちゃカラフル!!
紙もしっかりしていそうです。
(あとで調べたところ美濃和紙を使用しているとのことでした)
『え、これなに?なんなの?浮世絵・・・?』
めちゃくちゃ見入る自分。こんなカラフルな作品は初めて見ました。
と、そこに、座っていたおじさまが声をかけてくださいました。
「お客さん、芸術とかお好きなんですか?」
「はい、好きです。」
おじさまにっこり。
「これは確かに浮世絵です。美術の教科書に載っているようなね。
ただ教科書に載っているものは作者さんが一番有名な作品で、
こちらにある浮世絵は、現代の日本で、代々受け継がれてきた作者さん達の作品です」
わお!浮世絵って昔のものかと勝手に思い込んでいたのだけれど、
実は今現在も作品として作られているんだ?!
「ただし、もう浮世絵は、今後新しいものは作られません。
後継者がいなくなってしまいました。
いまこれを制作している方々もご高齢で80・90台の方が作られています。
次の入荷が終わってしまったら、もう新しいものは制作されません」
え、そうなの?!
「浮世絵は54枚や32枚など数枚で一組です。
浮世絵は版画ですから、1枚あたりでも幾つもの木造の版木を使います。
絵具は日本古来の顔料を使っています。
浮世絵が一枚完成するには、絵師・彫師・摺師という専門の職人さんがいて、
初めて成り立ちます。
年月を重ねるごとに、版木が欠けたり割れたりすると、
たとえ他の版木が無事でも、もうそのシリーズ(54枚組など)は作れません。」
えぇぇぇ!!!浮世絵ってすごく高等な技術で作られているんだなぁ!!!
めちゃくちゃ貴重じゃん!!
「この浮世絵を見てください。いくつもの版木が重なって着色されています。
版木で着色した上から、乾かして、更にまた版木で着色しています。
なので、浮世絵は作品を上から触ってみるとでこぼこしています。
試しに触ってみてください。」
え?いいんですか?これ売り物ですよね???
・・・うーん、まぁ販売員のおじさまがそう仰っているから触っていいのか・・・。
思わず好奇心に負けた私は、浮世絵の上に指を置いてそっと撫でるように触ってみました。
「あ、本当だ!エンボス加工されているようにでこぼこしてますね!!」
「そうなんですよ、ただの印刷ではないことがよくわかるでしょう?
お客さんが今触った触感と今見ているカラフルさは、
江戸時代の人々が見ていた浮世絵とまったく同じ紙の種類・同じ色彩なのです。
いま、貴方は江戸時代にタイムスリップしていたのです。
どうです?ロマンチックでしょう?」
そういって、浮世絵の販売師のおじさまは、
とってもうっとりとした表情で説明を終えました。
さてそこから丁寧にお値段のお話をしてもらったのですが、
流石にいまは自分自身に金銭的にも余裕がなく、
(何より歯医者さんの時間が迫っていたので)
すみません、ご説明いただきありがとうございました、と、
そそくさとその場を去りました。
とはいえ、人生でかなり貴重な体験をしたのでは・・・、と感じています。
興味をもって、浮世絵の美術館にでも行かないと、
ああいった丁寧な解説や造り、ましてや触らせてもらえることなんて、
本当にそうそうないですよね。
この体験は、昨年のクリスマス前後にしたので、
2024年を締めくくるにふさわしい、貴重な美術の体験だったなぁ、と思いました。
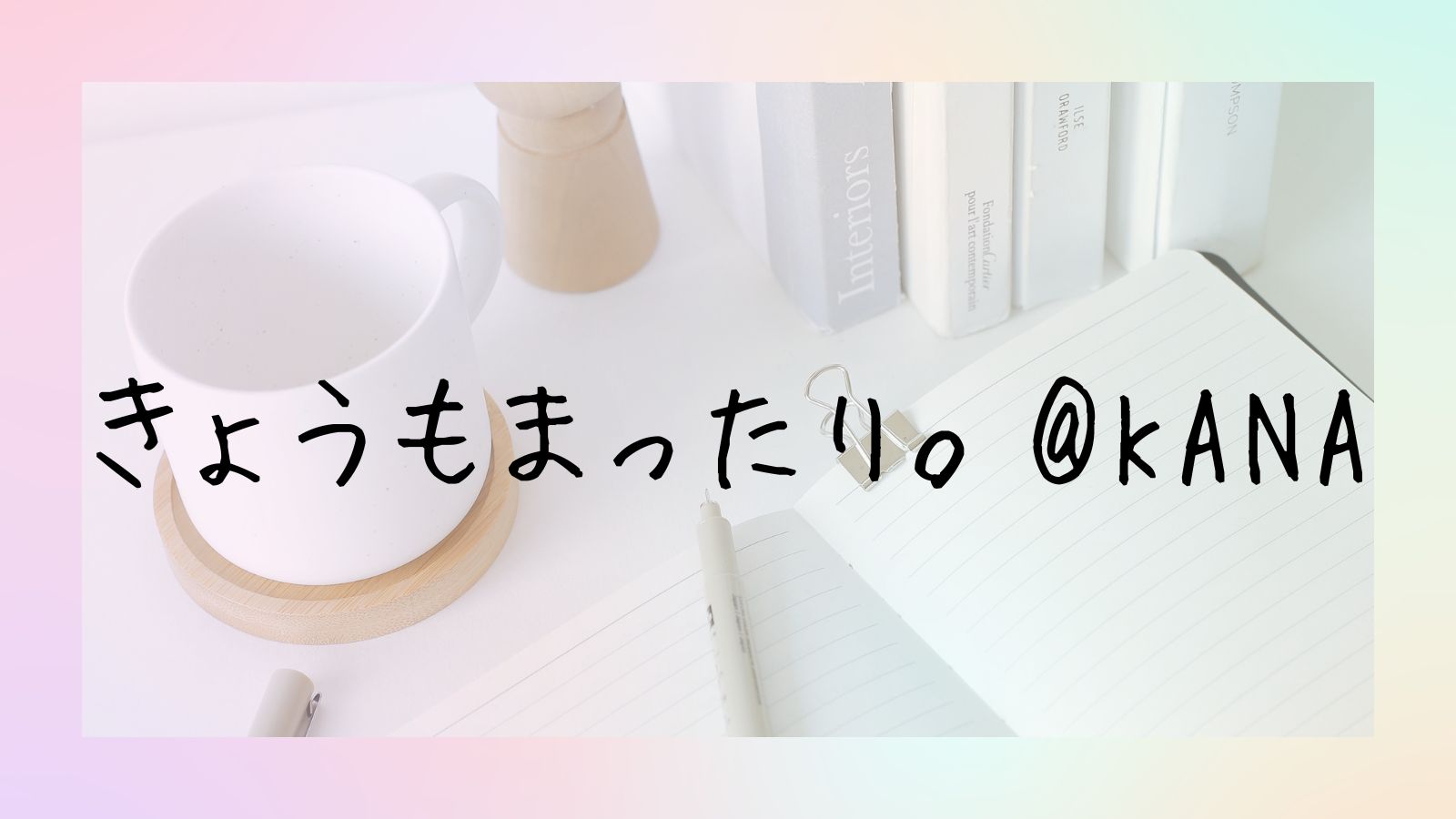


コメント